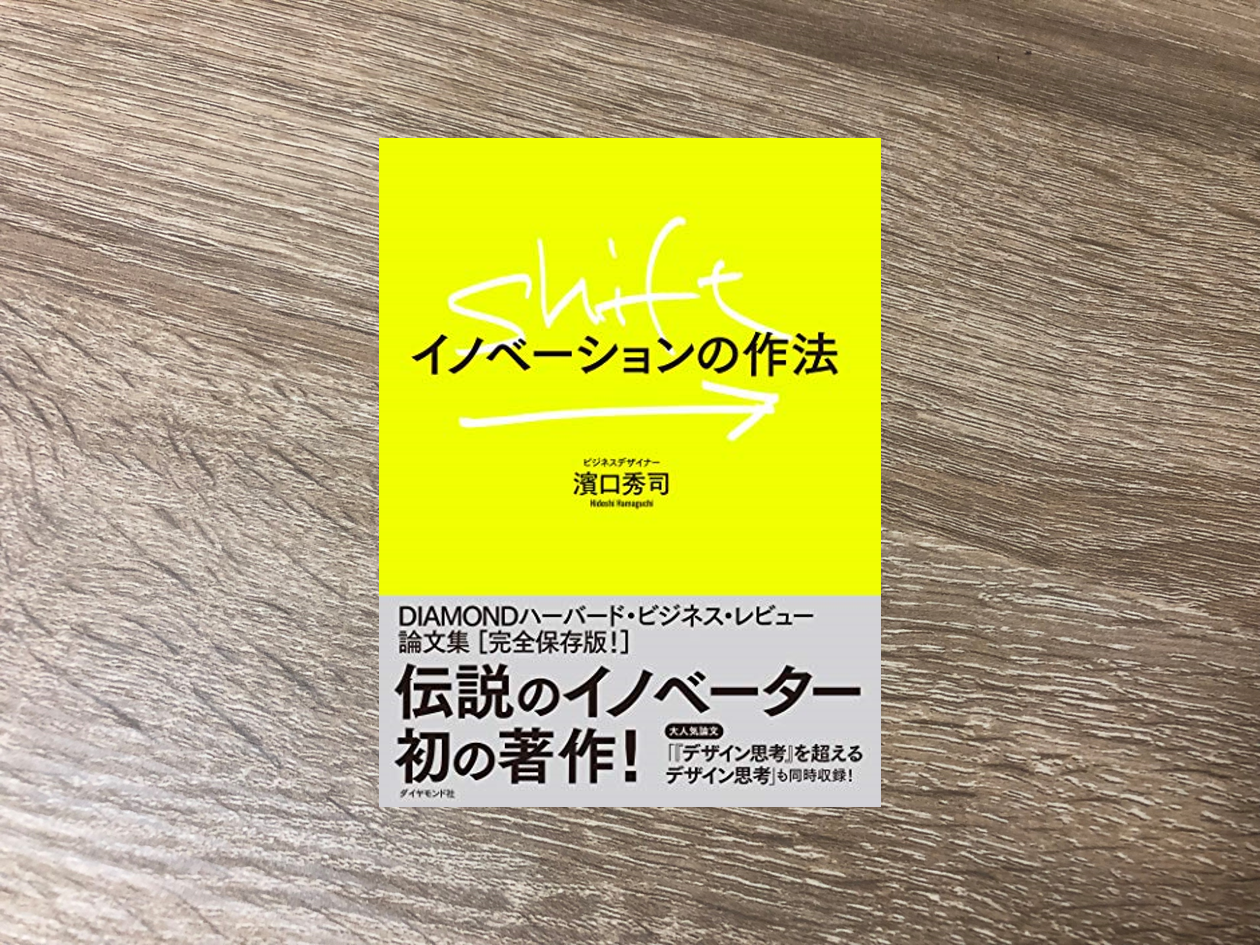内容
SHIFTとJUMP
企業の創造活動のあり方が問われている。
企業の創造活動には、連続的な変化(improvement:改善)と、非連続的な変化(innovation:革新)がある。
後者はさらに二つに大別でき、従来の事業領域やメンバーで新たな商品・サービスを提供する「SHIFT」と、ほぼ起業のような形で既存事業から離れた新規ビジネスを起こす「JUMP」に分けられる。
JUMPというのは、いまある事業領域から飛び地のエリアで新規事業を始めることである。
アイデアと中心人物と資金があれば、必要な追加リソースをその場で集めてきて、アイデアを中心に事業を新規に組み立てていくことができる。
もう一つのイノベーションの型がSHIFTである。
これはJUMPとは違い、既存の事業領域や所属メンバーをコアにして商品やサービスのあり方を規定し直し、市場の新しい認知を得ることで事業価値を高める設計手法である。
企業の基本的な機能
ピーター・ F・ドラッカーは「企業は二つの、そして二つだけの基本的な機能を持つ。それがマーケティングとイノベーションである」
イノベーション
イノベーションが生まれる現場で重要なのは、思考のモードを論理思考と非論理思考の中間に持っていくことである。
論理的すぎるのはもちろん、非論理的すぎてもいけない。
このイノベーションに適した状態を"structure"(構造・論理)と"chaos"(混沌・直感)の中間にある「ストラクチャード・ケイオス」(structured chaos)と呼んでいる。
アイデア出しの際には思考モードをこの状態にコントロールしなければならない。
また、これは個人で発想する際の思考モードの配分だけでなく、組織全体の構成にも当てはまる。
社内には、ロジカルなストラクチャー型も、直感的なケイオス型も存在している。
顧客体験やテクノロジーやビジネスモデルがイノベーティブであるほど、社内説得のハードルは高くなる。
誰もが簡単に思い付くアイデアではイノベーションが起こせない一方で、誰も思いも寄らないイノベーティブな発想ほど、社内の壁を超えることができない。
経営学が明らかにしてきたことのほとんどは、失敗しないための論理的な解であった。
近年の経営者や経営幹部、いわゆるディシジョンメーカーたちは、MBAやその他の機関で高度な経営論を学び、生産性からコスト管理、組織管理、マーケティングに至るまで、ありとあらゆる知識と理論を身につけている。
そんな経営理論の武装集団を前に、不確実性にあふれたイノベーションの実行を決断してもらうことは困難を伴う。
イノベーティブな発想とは、構造的にそういう宿命を背負っている。
β100
何よりも先に「こういうふうに買うはずだ」というコンセプトをつくり、それに基づいたプロトタイプをつくってしまう。
そして、疑似店舗を用意して、値段もつけ、想定されるメディアコミュニケーションのプロトタイプも準備したうえで、被験者一〇〇人に日常の買い物とまったく同じシチュエーションで買い物をしてもらう。
コストをかけずに、リアルな状況をつくり上げ、説得力のある数字を得る。
その結果によって不確実性が軽減され、初めて経営陣もリアリティをもって意思決定を行うことができる。
SHIFTの概念を最も端的に示すのは「矢印」すなわち「ベクトル」である。
それは「方向」と「大きさ」という二つの要素で構成される。
つまり、あらゆるビジネスの現場において「誰も思い付かなかった方向」を見つけ出し、「適切な大きさ」に調整して SHIFTが実現された時、それは結果としてイノベーションと呼ばれる可能性が高い。
イノベーションの三条件
❶見たこと・聞いたことがない。
❷実行可能である。
❸議論を生む。
実現不可能である以上、イノベーションではなくファンタジーでしかない。
〝コンセプト〟として語ることが大切である。
もう少し説明すると、「コンセプト」とはアイデアと切り口を合わせたものであり、「切り口」とは論理的で構造的な見せ方のことである。
切り口をセットにして語ることで、そのアイデアの強さを、論理的かつ構造的に示すことができ、ストラクチャータイプを説得する武器になる。
「β100」では次の三種のプロトタイプを作成することで総コストを抑えている。
デザイン・プロトタイプ:見た目、形状、手触りなどを忠実に実現する(ちなみに、英語で"design"は「設計」のニュアンスが強いため、海外では"aesthetic prototype"と呼んでいる)。
ファンクショナル・プロトタイプ:新たな機能を体感させる。
コンテクスチュアル・プロトタイプ:広告や取扱説明書などで、商品が持つコンテクスト(背景や文脈)を鮮やかに表現する。
注意してほしいのは、この三つを「混ぜないこと」である。
ディシジョン・マネジメント
ディシジョン・マネジメントはどのようなプロセスに、誰が関わって進められるのか、そのフローを簡潔に紹介しておこう。
全体の流れは、「セッション」「アセスメント」「モデル計算」「分析」「ディシジョン・ミーティング」という五つのフェーズで構成され、これらを約二週間で進める。
「質の高い意思決定とは何か」という本質的な問いを、常に念頭に置いておく必要がある。
なぜなら「アウトカム(意思決定をした結果)の質」と「意思決定の質」は必ずしもイコールではないからだ。
ユーザーの心をとらえる3つのアプローチ
- スナイパー型
- ハンター型
- フィッシャーマン型
①のスナイパー型アプローチとは、かなり離れた場所からユーザーの心を一発で射止めるアプローチである。
ユーザーという群衆の心理を的確に把握し、それに応える企画をつくる。
条件がすべて整った時、企画は一発で群衆の心を射抜き、ヒットとなる。
一昔前の、才能のあるプロダクトデザイナーや商業企画者は皆このスタイルだった。
どこに、どんな顧客がいるのかを予測してポテンシャルユーザーを見つけ、その心を射止める商品をつくるのだが、一発勝負なので外れる確率は高い。
ユーザー心理の把握が間違っていたり、ニーズに応えるに足る製品やサービスが設計されていないケースもあるからだ。
②のハンター型とは、より確実性を上げるために中距離からユーザーの心をうかがい、連続して複数の弾を撃つアプローチである。
ポテンシャルユーザーの存在をある程度絞り込んだうえで、彼らが反応しそうな商品を複数投下する。
無駄が生じるデメリットは避けられないが、スナイパー型と比べて命中率が向上するメリットがある。
購買意欲を駆り立てられる要素
ユーザーが商品を認知し、購買意欲を駆り立てられる要素には「デザイン」「ファンクション」「ストーリー」という三つがある。
原則として、ユーザーは「デザイン →ファンクション →ストーリー」の順に商品の特性を認知していく。
まずは見た目で感じ取り、次に機能を確認し、そのうえで商品に込められた物語を知る。
しかし、どの段階で、どの部分にいち早く反応し、購買意欲を抱くのかには個人差がある。
それらアウトドアスポーツを楽しむ際に、瓶入りワインを割れないように注意してバックパックに入れていき、ワインオープナーで開けてコップに注ぐ手間までかけて、わざわざ飲むだろうか。
その点、アルミ缶は軽くて割れる心配もないので、持ち運びに便利だ。
炭酸ではないので泡立ったり吹きこぼれたりすることもない。
アルミ缶は熱伝導性にも優れているので、川に浸しておけば冷えた白ワインを飲むこともできる。
飲み終えたら、缶を潰しコンパクトにして持ち帰れる。
缶入りワインには、それだけ多くのファンクションが備わっているのだ。
デザインにおいても、缶入りであること自体が強烈なインパクトを持つ。
パッケージデザインをシンプルに仕上げることも大切だが、それ以上に、「缶入りワイン」を一見するだけで「ワーカーがつくる、ワーカーのためのワイン」「カジュアルにアウトドアスポーツを楽しむ時に飲むワイン」というストーリーを雄弁に語ってくれる。
ストーリーの三要素が論理的、構造的に設計されていることは大前提である。
エクスターナルマーケティングでは「誰に」「何を」「どのように」働きかけるか、費用対効果に見合う形で企画することが重要である。
プロジェクト全体における時間配分
- コンセプト設計
- 戦略策定
- 意思決定
- 実行
自由度が高い上流フェーズに効果的にリソースを配分できるように意識しなければならない。
なぜなら、四つのフェーズのうち、ほぼゼロベースでシナリオを描けるという点で、①コンセプト設計や②戦略策定といった上流フェーズこそが、そのプロジェクトの成否を大きく左右しうるからだ。
一方、③意思決定や④実行といった下流フェーズは、決定されたコンセプトを実現するための行動であって自由度が低い分、その時点で方向性が間違っていたと思って是正したり、状況を一変させるウルトラCをひねり出すのは難しくなる。
私は「九〇:一〇の法則」があることにも気がついた。
イノベーティブなアイデアの九〇%は、プロジェクト全体のうち開始直後一〇%の期間内に思い付いているという事実である。
プロジェクトが一〇日あれば初日に、一〇〇日あれば最初の一〇日のうちに、ほとんどのプロジェクトでは〝答え〟を思い付いているのだ。
なぜプロジェクト開始直後一〇%の期間内で、イノベーティブなSHIFTにたどり着きやすいのか。
実は、これにもきちんと理由がある。
一つ目は、手元にある情報がシンプルなため、ハンドリングしやすい。
二つ目は、情報が本質的であり、核心を突いている。
三つ目の理由として、情報が少ないためにかえって想像力が働く。
コラボレーション
コラボレーションとは、「専門能力が高い複数のメンバーが集まり、頭数以上の成果を出すこと」であると明確に定義しておく。
実際に多くのプロジェクトで、専門能力を有したメンバーが集まり、ブレインストーミングやミーティングを行うことで「1+1=2を超える成果」を出そうとしていることだろう。
しかし、この段階ではっきり認識しておくべきは、「2を超える成果」が生まれるのは、コミュニケーションの行われる「場」ではなく、あくまで「個人の頭の中」である、という事実である。
コラボレーションで重要なのは「コミュニケーションの量」ではない。
重要なのは「個人が考え抜くこと」と「コミュニケーションの質を高めること」である。
チームでプロジェクトに当たる際、この点に気をつけて時間と思考をマネジメントしなければならない。
まず、個人で考え抜いているからこそ、「完璧にシンプリファイされたコンセプト」(アイデアと切り口)を語ることが可能となる。
それを聞く側も、一度自分の頭で考え抜いているからこそ、相手のシンプルなアイデアを見た瞬間、その作品の面白さや、切り口の斬新さを即座に理解することができる。
この「シンプルに語れる」「アイデアの価値を即座に理解できる」という状態は、コミュニケーションの質を高める重要な要素である。
また、アイデアをシェアする際に「アイデア」と「切り口」をセットで語る点にも重要な意味がある。
換言すれば、これは「具体」と「抽象」を提示することになる。
自分のアイデアとともに、なぜそれがいいのか発想の軸を示してシェアすると、それぞれの切り口を組み合わせ構造化して、認知バイアスが「見える化」され、それを超えるアイデアを生み出しやすくなる。
コラボレーションを成功に導くポイント
- シンプルに語る
- 箱に入れる
- アップグレードする
「シンプルに語る」というのはコミュニケーションの質を高める最重要ポイントである。
特に異種メンバーが交わるプロジェクトでは、必須である。
前提として、互いが持ち合わせている知識や経験、バックボーンがまったく異なるので、究極的に単純化しなければ、話す内容を共有できない。
「箱に入れる」というのは、議論のテーブルに乗せられる状態になっていることを指す。
「写真に撮る」「絵を描く」「ホワイトボードに書く」など様式はどれでもいいが、それぞれのメンバーが考えた「究極にシンプリファイされた結果」がきちんとどこかに格納されていなければならない。
「アップグレードする」というのは、前述の実験でCチームが実践したような「箱に入った材料を使って、バイアスを見出し、よりよくする」というプロセスである。
これも、コラボレーションには欠かせない。
人材教育
「人材教育」を定義すると、教える側が持つナレッジ(知識や経験)を学ぶ側にダウンロードすること、である。
さらに、このナレッジは「やるべきこと」(what)と「やり方」(how)、そして「文書化できるもの」と「文書化できないもの」に分けて考えられるので、「ナレッジを分解する」の通り四種に整理できる。
各コンポーネントの関連性やその全体像は明らかにしない。
このさじ加減が大切だ。
すべてのコンポーネントが合理的かつ精緻につながっている。
ただし、その全体像を伝えるとパターンAにはまってしまうので、それは避ける。
おそらく、学んでいる人たちは「一つひとつはすごく納得できるけれど、全体はボヤッとしている」という感覚を覚えるだろう。
全体像を、自分なりに必死に考える。それこそが、大事なのだ。
イノベーションを:
❶知っている。
❷理解する。
❸一人でできる。
❹グループをリードできる。
❺教えることができる。
この五段階の「どこ」を目指して、「どのぐらいの期間」で到達させるのか。
一日なのか、一カ月なのか、一年なのか、五年なのか。
出発点でそうした設計がないと、効果的な育成はできない。
イノベーションを起こせる人材である。
より具体的に言えば、「ストラクチャー(構造・論理)型」と「ケイオス(混沌・直感)型」双方の思考バランスに優れた「ストラクチャード・ケイオス」型である。
彼らは学習速度も速い傾向にある。
教える側の役割は究極的に次の三つしかない、と思っている。
相手の心にやる気の火を灯すこと、そして自分を凌駕し取って代わられそうなほど優秀な刺客に育て上げること、さらに、その刺客にけっして負けないこと。
3K
会社の中で新しいことを始める時は、なかなか前に動かないものである。
しかし、それまでどうしても動かなかったものが突然動き出す、ということは実際にある。
その条件となるのが「3K」だ。
一番目は「競合」である。
ライバル会社がDMをやり始めたら、うちもやろうか、という話になりやすい。
それまで社内が渋っていた新製品も、ライバルが似たような製品を出すという情報が入ると、急に進み始めたりする。
二番目は「協業提案」である。
社内の提案は聞く耳を持たなかったのに、外部から「こんな話があるので一緒にやりませんか」と似たような協業の提案が来ると、意思決定者も真剣に考え始めたりする。
最後の三番目は「狂人」だ。
発案者が常識を打ち破るほどの熱意で取り付かれたように意思決定者に迫れば、社内は動く。
それも、将来の幹部と目される伸び盛りの人材であれば、なおさら動きやすい。
そして、相手に主張して納得させるために不可欠なのは、パッション(情熱)、アイデア、ロジックの三つである。
「僕にはパッションはあるのに、うちの経営者が石頭で理解してくれない」という場合も、よくよく話を聞くと、アイデアが面白くないか、ロジックがないか、ということが多い。
デザイン
前者はいわゆる狭義のデザインであり、商品やロゴ、広告や店舗における形や美的スタイルをつくることを指している。
これに対して後者は、デザインという言葉が本来持つ広義の「設計」を意味し、ビジネスにおける問題解決や、コンセプト・戦略・マーケティングの設計を指す。
IDEOやZibaのような一部のデザインファームは、右下から右上の象限に移行した。
つまり、狭義のデザインに留まらず、ビジネス上の問題解決などを設計する手法としてデザインをとらえ始めたのである。
一般に「デザイン思考」といわれるものはここの領域で使われる。
彼らは、インテグリティ(完全性)ソリューションを前面に打ち出した。
ここでIDEOが、デザインファームの問題解決手法がイノベーションにつながる、と非デザイナーに向けてマーケティングを行ったことにより、「デザイン思考」は一大ブームを迎えたといえる。
現代は、これまで活躍してきたような、断片的にイノベーティブなアイデアを思いつく「普通の天才」にとって受難の時代を迎えている。
なぜなら、いま行われている競争とは、「B」(Business model:ビジネスモデル)、「T」(Technology:技術)、「C」(Customer experience:顧客体験)という三領域それぞれのアイデアを組み合わせた、総合的な設計者同士による高度なものであるからだ。
面白かったポイント
思考を整理する切り口が面白い。
こういう本は好き。
満足感を五段階評価
☆☆☆☆☆
目次
はじめに 刊行記念序文「日本人イノベーション最強論」
第1回 イノベーションは誰もが起こせる
第2回 SHIFT領域の考え方
第3回 バイアスを破壊する
第4回 問題の本質から強制発想する
第5回 市場を実験場にしない
第6回 不確実性の中で意思決定を下すには
第7回 戦略意思決定の質を高める
第8回 ユーザーの心をいかにとらえるか
第9回 誰に何をどのように働きかけるか
第10回 プライシングを動的にとらえる
第11回 自由度の高いフェーズにリソースをかける
第12回 個人で考え切ってこそ議論の質が上がる
第13回 学ぶ者が教える者を超えなければ意味がない
第14回 不確実性を論理的に乗り越える ~SHIFTに関するQ&A